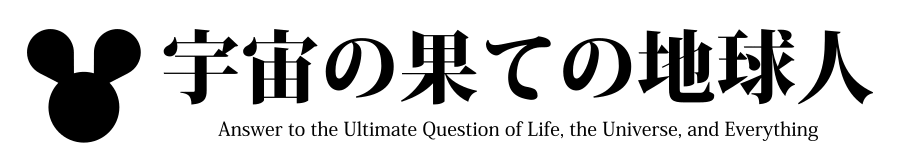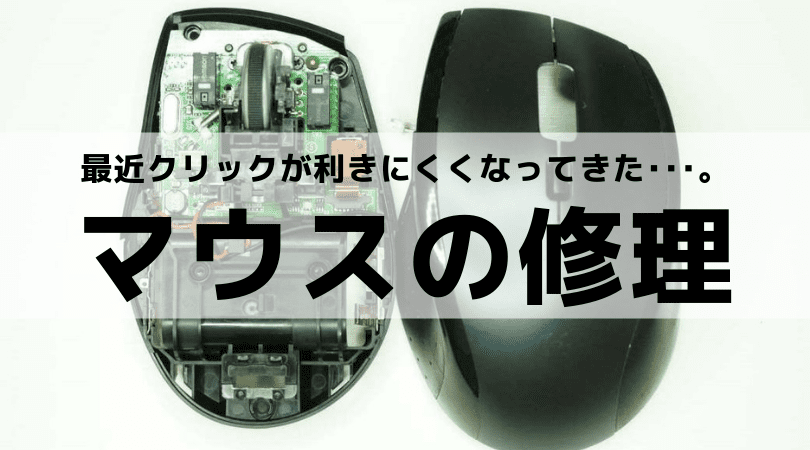食レポです。
- 釣り旅行に行って、見慣れない魚をたくさん釣った。
- 調べたところキントキダイ科キントキダイ族(ホウセキキントキとアカネキントキ)だと思われる。
- これらの魚を、いくつかの方法で調理して食べてみた!
このツイートが釣れた当時のものです。
昨夜から今朝のことですが…
— うちゅーじん (@uchujin556) December 8, 2019
赤くて目と口の大きい、おいしそうな魚がたくさん釣れました😃✨
本種を知っているだけで、食生活が向上すると言っても過言ではない。
らしい。#チカメキントキ pic.twitter.com/4edox2Hviu
釣り上げた瞬間は大きな目がキラッと光ったので「キンメダイか??」と思いました。そしてツイートではチカメキントキと書きました。どちらも間違いで、後から調べてみるとホウセキキントキとアカネキントキの両方が混ざっていた可能性が高いことが分かりました。
釣れた魚の紹介

上がアカネキントキ、下がホウセキキントキ、だと思われます。分かりやすい違いは尾びれの形状です。
調理中に腹膜の色が違うことにも気付きました。

アカネキントキは黒色ですが、ホウセキキントキはほぼ無色です。(もし間違っていたらどなたかご指摘お願いします。)
ホウセキキントキについて
比較的暖かい海域の岩礁機にいる。刺し網や釣りでとれるが量的には少ない。関東では珍しい魚ではないが、探しても必ずあるとは限らないといったもの。非常においしい魚であるが、その評価は味に対して低すぎる。大型は高級魚になってもおかしくない。
ホウセキキントキ|魚類|市場魚貝類図鑑
釣れた数はホウセキキントキの方が圧倒的に多かったです。
アカネキントキについて
徳島県海部郡海陽町宍喰では雑魚として扱われている。味がいい魚なのでまことにもったいないと思う。
アカネキントキ|魚類|市場魚貝類図鑑
アカネキントキは、ホウセキキントキに紛れて少しだけ釣れていたようです。調理中に気が付きました。
どちらも同じキントキダイ科キントキダイ属の魚で「非常に美味」らしいです。ちなみに、キントキダイ科キントキダイ属の魚は調理の段階でウロコを取り除くことが難しいらしいです。硬く細かいウロコに全身が覆われているおかげでサンゴ礁や岩礁に体をぶつけてもケガをしないのだとか。

ウロコの質感がよく分かる写真を載せておきます。
食レポ(簡易レシピ付)
初めて入手した魚なので、いろいろな調理方法で食べてみて感想を書きます。あくまで素人の調理と個人的な感想です。ちなみに、アカネキントキよりもホウセキキントキの方が釣れた数が圧倒的に数が多かった上に、区別せずに調理しています。よって、全てホウセキキントキの食レポだと考えると良いと思います。
お刺身(評価★★★☆☆)

あっさりとした白身で、すごくお上品です。ただし、あっさりとしすぎていて、やや物足りなさを感じました。ちなみに、釣った翌日に食べました。熟成させると違った感想になると思います。
- ウロコを取り除かずに三枚おろしにする
- 皮をひく(同時にウロコも取り除かれる)
- 中骨と肋骨を取り除く
- スライスする
- 完成!
昆布締め (評価★★★★★)

お刺身を昆布で挟み込んで2日間ほど熟成させたものです。普通のお刺身だと物足りなさがあったので試してみることにしました。食べてみると・・・これは、美味しい!味の変化はもちろん、熟成することで歯応えも変化しています。魚の味が凝縮されるだけでなく、昆布のエキスが染み込んで旨味も濃厚です。もちろん一日目より二日目の方が風味が濃厚です。
- だし用の昆布を軽く水で戻し、お刺身の冊を挟む(冊の数だけ何層も重ねる)
- できるだけ空気を抜くようにラップでぐるぐる巻きにする
- 冷蔵庫で熟成させる(1日~2日)
- 完成!(食べやすいようにスライスしましょう)
個人的には1日目の方が好みでした。二日目のものは昆布の風味が強すぎて、お刺身の歯応えのする超美味しい昆布を食べているようでした。結局は美味しいのです。
潮汁 (評価★★★★★)

美味しい!これは素晴らしく美味しいです。あっさりとしていますが、物足りなさはありません。お上品さと味わい深さを兼ね備えた素晴らしいスープになりました。料亭の味。お刺身を作ったならぜひ作りたいメニューです。お刺身を作らない限り、潮汁を作る機会はないと思います。
- お刺身を作った残りの部分(あら)を熱湯で素早くきれいに洗う
- お鍋に昆布と水を入れて沸騰させる
- あらを入れて弱火で5分ほどコトコトする
- 塩と醤油で味を調整する
- 火を止めてミツバを入れる
- 完成!
煮付け(評価★★★☆☆)

美味しい!!だけど身と皮がくっついていて、ウロコも一緒にしつこく付きまとってきます。もしウロコが口の中に入ってくると、お口の中が砂嵐状態になりザラザラと不快です。ウロコさえなければ、と思いますが、そもそもキントキダイ科キントキダイ族の魚はウロコを取り除くのがすごく難しいのです。料理すると分かるはず。もちろんレバー(肝臓)も美味。
- 水:酒:醤油:みりん=3:1:1:1の比率で魚が浸るぐらいの量を鍋に入れを沸騰させる
- 魚を入れて、落し蓋をして15分ほど煮る(魚の大きさによって調整しましょう)
- 完成!
塩焼き (評価★★★☆☆)

美味しい!だけど、こちらもウロコのせいで評価を下げました。煮付けと比べると直火に晒しただけあって砂嵐感は弱めですが、やはりザラザラと不快です。
- 塩をふる(頭やヒレに飾り塩をすると良い)
- グリルで両面を焼く
- 完成
唐揚げ(評価★★★★★)

うん、やっぱりすごく美味しい。想像していた通りです。厄介だったウロコがカラっと揚がっていてすごく食感が良く香ばしいです。マイナス要素だったウロコをプラスにできる調理方法なので素材の特徴も活きてきます。そして二度揚げしたので骨までカリカリサクサクと食べられます。調理が大変だしキッチンが汚れるのが難点。
- 鰓と内臓をきれいに取り除く
- 魚の背側から背骨にかけて切れ目を入れる(魚の上半分だけを三枚おろしにする感じ)
- 魚を隅々まで片栗粉でコーティングする
- 軽くたたいて余分な片栗粉を振り落とし、180度に熱した油へ投入する
- 10分後に油から取り出し、5分ほど冷ます
- 200度に熱した油へ投入し、3分ほど揚げる(いわゆる二度揚げ)
- 完成
塩モリモリ焼き(評価★★★★★+★)

この調理方法は、調理の難易度や味などから総合的に判断して僕が最も良いなと思ったものです。すごく簡単ですごく美味しい。塩焼きとの違いは、塩の量です。ウロコを付けたまま調理せざるを得ないキントキダイ科キントキダイ族の魚です。普通に塩焼きにしてしまうと身とウロコがくっついてしまい、結果的に大量のウロコがお口の中に入ってきてすごく不快でした。このウロコによる口内砂嵐問題を、塩の量を増やすことで解決しました。塩の量はたぶん塩釜焼と塩焼きの中間ぐらいです。ちなみに塩釜焼では卵白を使いますが、今回の塩モリモリ焼きでは面倒だったので卵白は使っていません。写真を見て分かる通り、身と皮が剥がれやすく非常に食べやすく仕上がりました。
- 魚に塩を盛り、霧吹きで水を吹きかけて塩を密着させる
- 裏返して反対側にも塩を盛り、霧吹きで水を吹きかける
- グリルに入れて、塩の表面がこんがりするまで焼く
- 裏返して反対側も塩の表面がこんがりするまで焼く
- 完成(塩を剥ぎ取りながら食べる)
まとめ
キントキダイ科キントキダイ族の魚(ここでは特にホウセキキントキ)はすごくお上品な味でした。どんな調理方法でもすごく美味しく食べられました。ただ、とにかくウロコが厄介!ウロコ問題を簡単に解決できる調理方法として、僕は超簡単ですごく美味しかった塩モリモリ焼きを紹介しました。他にも適した調理方法はあるはずなのでぜひ試してみてください。